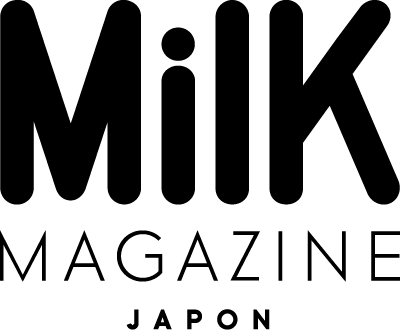Innocent View 北島敬三
「自分の作品というだけじゃなく、写っている人のものでもある。だからプリントして大事に残していかなきゃいけないと思った」北島敬三
——1970〜’80年代、都市とそこに生きる人を捉えた緊張感のあるストリートスナップで名を馳せた北島敬三さん。その後’90年代から大きくスタイルを変え、スタジオの真っ白な背景で白いシャツを着た人物を定期的に何年にもわたって撮り続ける『PORTRAITS』シリーズや、人の姿がまったく見あたらない景観の記録『UNTITLED RECORDS』シリーズに現在に至るまで取り組んでいる。スタイルを変えながら写真を撮り続けてきたなかで、写真家としてものを見る、写真を撮る、そして発表するということはどういうことなのだろうか?——
「森山大道かっこいい」からモダニズムの潮流の中へ
ストリートスナップからスタジオでのポートレート、ランドスケープなど、これまでに撮ってきた写真を見て、スタイルが大きく変わっているとか、全然違うものを撮っているとか思われるかもしれないけど、変わっているようで変わっていないところもやっぱりある。自分ではそう思っています。
子どもの頃、写真ってとにかくかっこいいものだったんです。高度経済成長期に広告写真が大きく力を持つようになって、写真雑誌を普通の人も読んでいるような時代でした。中学生ぐらいだったかな、同級生に写真好きがいた影響で、「写真って面白いな」と思うようになったんです。雑誌『アサヒカメラ』の森山(大道)さんの連載は高校生くらいの時から見てましたね。
地元の高校を卒業した後は東京の大学の法学部に進学したんですけれど、なんとなく大学を卒業してなんとなく就職するのは嫌だなと思っていて。なにか、例えば音楽とか、そういうことをやりたかったわけです。だから『アサヒカメラ』に載っていた森山さん主宰の「WORKSHOP写真学校」の告知を見て「これだ!」と。森山大道といえば、今までの写真という概念を超えたものを発表しながら、その表現にはどこか社会に対する怒りのようなものも感じられる写真家で、すごくかっこいい存在だった。「俺も写真家になろう」と決めて大学を辞めました。とにかく一生懸命やろうと思って写真を始めたわけです。
「WORKSHOP写真学校」では、森山さんだけじゃなくて東松照明とか中平卓馬もいて、彼らの考えややっていることに触れることになるわけですが、しばらくしてから、自分が戦後の写真の歴史、戦後日本のモダニズムの歴史の流れのただなかにいるんだ、ということに気がつきましたね。
撮ることで人を傷つけてしまったり自分が傷ついたりする
そのあと1976年に森山さんたちと立ち上げた自主運営ギャラリー「CAMP」で、自分の作品として最初に撮ったのが東京と沖縄のコザ市でした。当時、写真表現というものは、自分の表現意図を消し去って、手を加えずに現実を記録するべきだという考え方がどこかにあったから、ストロボを使って撮り始めたんです。街の猥雑で怪しげな路地の奥をストロボの光で照らせば、何か真実の世界につながる入り口が見えるんじゃないかと思っていたんですよね。でも、だんだんに「違う」と感じるようになって、その後ニューヨークを撮りに行った時にはストロボは半分、その次にヨーロッパに撮影に行った時にはもうストロボは持っていきませんでした。
沖縄を撮影して気づかされたのは、自分を含めて誰だって歴史と無関係ではいられないということ。本土の人間がずっと沖縄に酷いことをしてきた歴史があって、自分はその文脈の中で現地の人から「ヤマトンチュ※」と呼ばれるわけです。自分という存在はピュアな存在で、カメラが起こす純粋な事故のようなものがあると思っていたらそれは大間違いでした。
現実を記録するといっても写真はメモとは違います。写真を撮るという行為の責任の主体は自分です。写真を撮ることで人を傷つけてしまったり、あるいは撮る側が傷ついたりすることもあります。つまり、写真を撮るということは、見る側と見られる側という非対称の権力構造の中に身を置くことなのだと思うのです。
そういったことは沖縄に滞在して撮らないと分からなかったことだし、東京と沖縄を同時に撮っていたから気づけたことだとも思うんですよね。2つの場所を撮りながら、ハイブリッドに考えるのは自分の癖かもしれません。ニューヨークに行って初めて東京についてちゃんと考えられるとか、ソウルに行って初めてパリについてちゃんと考えられるとか、そういうところがあるんです。

©Keizo Kitajima
著作権や肖像権、写真は誰のものなのか?
人の顔と街っていうのは、合わせ鏡みたいに渾然一体とした関係性にあったと思います。人間の欲望は街にそのまま映るし、逆に街の欲望も人間の顔に表れていました。でも、時代とともに街からはどんどん怖い場所や闇に覆われた場所がなくなり均質化して、その関係に亀裂が入っていくような感じがしたんですね。それで、街を撮るのがつまらなくなってしまった。だったらいっそのことその亀裂を受け入れようと考えて、それで、人の顔を撮るシリーズの『PORTRAITS』と、街の景観だけを撮る『UNTITLED RECORDS』の2つのプロジェクトとして、人の顔と街を別々に主題化して撮ることにしたわけです。
1992年に『PORTRAITS』を始めて以降、昔の写真が嫌になって捨ててしまいたいと感じるようになりました。実際、ほとんど捨てしまったんですよ。過去の写真は自分が一度ダメ出ししたものだと考えていましたから。でも、ふとある時に昔の写真を見たら、そこに写ってる人たちがかけがえのない存在に思えたんです。写真の中にはすごく仲の良かった人たちもいたし、沖縄にコザ市はもうないしね。それらはもう二度と写らないもの。写真は自分の作品というだけじゃなく、写っている人のものでもあるのだ、と。だからプリントして大事に残していかなきゃいけない、と。
写真の著作権っていうのは撮影者にあるわけだけれど、写っている建物にも著作権はあるし、写っている人には肖像権がありますよね?だから、写真は誰のものかっていうと曖昧なんです。写真って、いわゆる美術作品とは違って、本来そういう媒体なんだと思います。
※沖縄の言葉で本土の人の意味。
Top Photo ©Keizo Kitajima
Text: Chiaki Seito
北島敬三
1954年、長野県生まれ。1974年にWORK SHOP写真学校の森山大道教室に入学。1976年に森山大道ほか、WORK SHOP森山大道教室の卒業生とともに自主運営ギャラリー「CAMP」を立ち上げる。以降、東京、沖縄のコザ、ニューヨーク、旧ソ連、東ヨーロッパ、ソウルなどの街と人を捉えた写真を発表。1992年からは20年以上にわたってスタジオでのプロジェクト『PORTRAITS』に取り組む。また、風景写真のシリーズ『PLACES』『UNTITLE RECORDS』の撮影を続ける。1983年に『NEW YORK(』白夜書房)で木村伊兵衛写真賞受賞。2022年『UNTITLED RECORDS』シリーズで第41回土門拳賞受賞。https://pg-web.net/