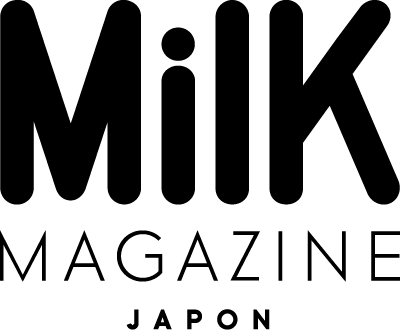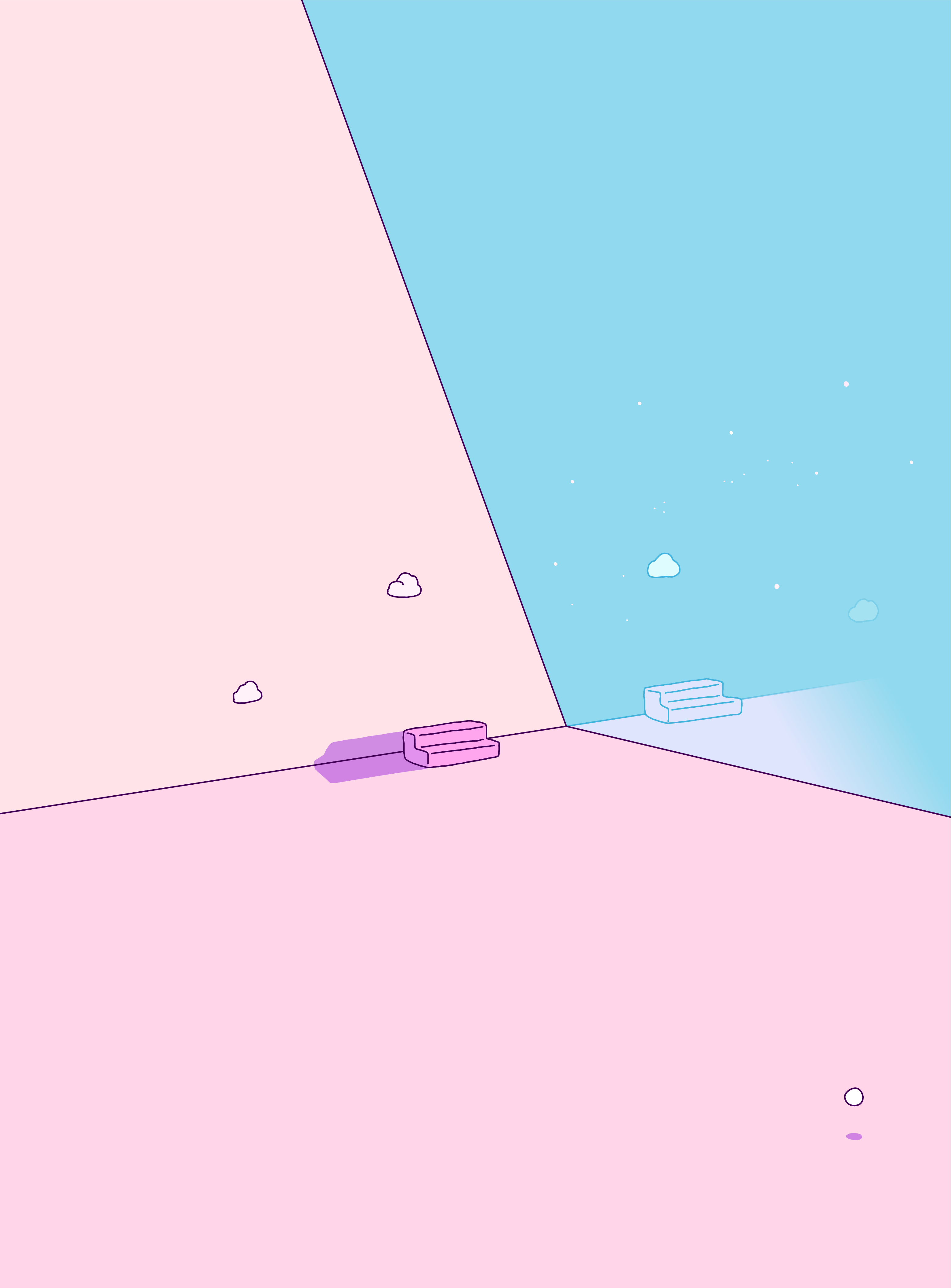A Sense of Wonder 扉の開け方「科学と出会う時」
——子どもの世界は、驚きや不思議にあふれています。日々の中で子どもたちはそれらの扉をひとつひとつ開け、何かを感じて自分なりの解を得ながら成長していきます。子どもはどうやって扉を見つけ、そして開けるのか? その時、大人はどう寄り添う? 今回は、子どもと科学のお話。子どもが科学と出会うきっかけ作りに取り組んでいる福田大展さんは、子どもたちの目に映る純粋な驚きこそが、科学との最初の出会いではないかと言います。——
たとえ大人たちと同じ風景を見ているとしても、子どもたちの眼の底には違うものが映っている
「雪は天から送られた手紙である」という言葉を残した物理学者・中谷宇吉郎の故郷、石川県加賀市を訪ねた。雪の結晶の美しさに魅せられ、世界で初めて人工雪の結晶を作った人物である。私の旅の理由は『中谷宇吉郎随筆集』(樋口敬二編、岩波書店)の一篇「簪(かんざし)を挿した蛇」に綴られている、宇吉郎が幼少期をすごした小学校の裏山に行ってみたかったからだ。随筆によると、その山にはある伝説が残っていて、江戸時代に山頂にあった城が攻め落とされて奥方や姫が亡くなり、城跡に《簪をさした蛇》の姿に化けて現れるという。私は城跡を1時間ほど散策し、ついに蛇とは出会わなかったのだが、本丸跡に立つ楓(かえで)の大木を見つけて子どもの頃のある記憶にさらわれた。
小学生の頃のある夏の日、実家の庭にある背の高い楓の木にイラガの幼虫が大発生した。刺されると電気が走ったように痛いと恐れられる毛虫である。特撮怪獣映画に出てくる「モスラ」の幼虫が進化して毒針を身につけたような“トゲトゲ毒毛虫”の出現に、少年の頃の私の胸のうちにスクリーンでの戦いがよみがえった。毒針に刺されたら飛びあがるほど痛いから気いつけなあかんよ、との祖父の戒めは恐怖心を植えつけるどころか、毒針という不純なものだけに許される独特の響きに魅了され、どのようにこらしめたものかと作戦を練るのにわくわくする始末だった。
私はまず、割り箸でつまんだ敵を縁側にとらえて観察することにした。イラガの身体は真夏の陽ざしを浴びて輝いて見え、じっと眺めているうちに、縮尺の感覚がまひしてイラガの世界に吸いこまれ、棘(とげ)がパチパチと細い火花を散らす線香花火の「松葉」のように見えてきた。背中には虹が架かったような筋がある。瑠璃色、翡翠色、柳色、朱色。図工で使う12色の絵の具では表現しきれない、源氏物語の十二単のように繊細な色を重ねた姿に、思わず見惚れてしまった。そこに立ち現れたのは、トゲトゲ毒毛虫ではなく、まったく別の美しい生き物だった。なんでこんなにきれいに左右対称の模様になるんだろう。毒はどんな時に使うんだろう。毛虫の世界であふれた私の頭の中には、誰かのいろんな声が盛んに飛び交っていた。
先ほどの随筆の中で宇吉郎はこう語る。
本統の科学というものは、自然に対する純真な驚異の念から出発すべきものである。不思議を解決するばかりが科学ではなく、平凡な世界の中に不思議を感ずることも科学の重要な要素であろう。(『中谷宇吉郎随筆集』P.76)
今になって思う。あの夏の日の毒毛虫に感じた、線香花火や十二単の色の重なりこそ《本統の科学》との出会いだったと。あの時心に渦巻いたものこそ《純真な驚異の念》だったと。
子どもの眼に《純真な驚異の念》が宿った時、身近な大人に何ができるだろうか。たとえ大人たちと同じ風景を見ているとしても、子どもたちの眼の底には違うものが映っている。随筆の続きで、宇吉郎はそんな荒唐無稽な非科学的なものでさえも大事にしてはどうかと訴える。
幼い日の夢は奔放であり荒唐でもあるが、そういう夢も余り早く消し止めることは考えものである。海坊主も河童も知らない子供は可哀想である。(同、P.77)
幸いにも、私は自由な発想を妨げられず奔放に育てられ、想像の世界の手足をのびのびと広げることができた。《純真な驚異の念》に対して、そんな寄り添い方もある。
本丸跡に立つ楓の梢をじっと見つめていると、羊歯(しだ)に覆われたほの暗い影から黒い翅(はね)を透かしたトンボが軽やかにすぎていき、ふいに視線をさまよわせると、その先の藪が開けて眼下に宇吉郎の母校が広がり、陽に焼けた球児たちがキャッチボールをしているのが見えた。現代を生きる彼らの眼には、故郷の山や川や湖に棲む生き物の姿はどのように映っているのだろう。海坊主や河童を見ることはあるのだろうか。故郷の自然の中でも、人工物の中でも、この世のものでもあの世のものでもなんだっていい。子どもの頃の純真な驚きを、大切にしまい続けてくれたらいいな。
宇吉郎は故郷で感じた荒唐無稽なものたちを生涯にわたり愛した。随筆はこうしめくくられる。
眼に見えない星雲の渦巻く虚空と、簪をさした蛇とは、私にとっては、自分の科学の母胎である。人には笑われるかもしれないが、自分だけでは、何時までもそっと胸に抱いておくつもりである。(同、P.82)
帰り途、山の麓にある図書館で昆虫図鑑をめくり、城跡を翔んでいたトンボが「羽黒蜻蛉(はぐろとんぼ)」だろうとつきとめた。お盆の頃に現れ、ご先祖様が姿を変えた「神様トンボ」とも呼ばれるらしい。トンボとなって立ち現れたのは、江戸時代の姫か、はたまた3年前に亡くなった祖父だったのかもしれない。
福田大展
公益財団法人 稲盛財団職員。福井県福井市生まれ。 東北大学大学院理学研究科修了、修士(物理学)。中日新聞(東京新聞)記者として東日本大震災や原発事故を取材するなかで、日常で科学技術について語り合う場の大切さを感じ、日本科学未来館(東京)で科学コミュニケーターとして勤務。その後、科学雑誌『Newton』編集者などを経て現職。子どもが科学と出会うきっかけを作る「こども科学博」(イベント)や「キヅキランド」(WEB サイト)などのプロジェクトに携わる。共著に『天野先生の「青色LEDの世界」』(講談社ブルーバックス)。
Text: Hironobu Fukuda
Illustration: Yuki Maeda