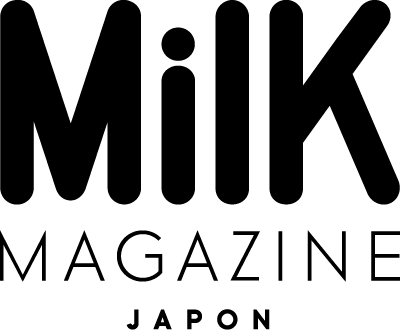実話を元に制作された新作映画『パリ・ブレスト 〜夢をかなえたスイーツ』。モデルとなったパティシエ、ヤジッド・イシュムラエンにインタビュー
モロッコ出身という両親の元、フランスに生まれたヤジッド・イシュムラエン。父親は不在、母親はアルコール依存症だったため2歳からホストファミリーに預けられ、その後8歳で養護施設へ。そんな彼が出会ったお菓子作りは、彼の人生を大きく変えていくことに。ヤジッドの自叙伝『Un rêve d’enfant étoilé: Comment la pâtisserie lui a sauvé la vie et l’a éduqué(星の少年の夢:菓子作りが彼を救った理由)』を原作とした最新映画『パリ・ブレスト 〜夢をかなえたスイーツ』が、この春公開される。子ども時代の葛藤から、彼が夢を実現するまでをリアルにそして色鮮やかに描ききった本作は、がんばることの意味や生きる目標について、私たちに多くの気づきを与えてくれる。5度目の来日を果たした世界的パティシエでもあるヤジッド。自らの幼少期をかえりみて感じること、これからの未来を担う子どもたちへの想いなどをインタビューした。

映画『パリ・ブレスト』は、短い時間に凝縮されたご自身の濃密な人生を改めて振り返るキッカケになったのではないですか?
5年前に書いた自叙伝から今回の映画化まで、さまざまな形で自分の人生を振り返りました。当時は資金がなくて出版社も見つからなかったので、友人に印刷を頼むなどして自費出版をしたんです。パティスリーの世界選手権でチャンピオンを取った直後でしたから、すぐにたくさんの映画会社から映画化のオファーが来ました。いちばん大切にしたかったのは、自分の真実を語れるこいうことだったから、それを実現してくれた監督や脚本にはとても感謝しています。
自叙伝を書こうと思ったいちばんの動機は、なんだったのですか?
僕にとって、パティスリーの世界選手権での優勝は、もうそれしか選択肢の余地がなかったからなんです。今まで過ごしてきた人生から区切りをつけるため、人生の次の1ページをめくるため、苦しい過去から抜け出すためには、絶対にやらなくてはいけないという私にとってはたったひとつの選択肢でした。
チャンピオンになった時、苦しい時代から次の1ページをめくることができた……と思いました。でも同時に、なんていうか、虚無感みたいなものに襲われたんです。ちょっと鬱っぽくもなりました。その時に自叙伝を書き始めたんです。今まで自分がやってきたことに何か意味を与えたかった。自分にとっては、人生を文字にすることが、どこかセラピーのような意味合いがあったと思うんです。
勝つことだけが目的だったのではなく、私がどんな人生を送ってきたかを表現することが、もう一つの大切にしたい目的でした。今を生きる若い人たちの中に、たとえば同じような境遇だったり、毎日が苦しくてなかなか前に進めなかったりする人がいたら、私の書いた本を読むことでひょっとしたら乗り越えることができるかもしれないと、思ってもらえることが大切だったんです。

ヤジッドさんは若干14歳で、パリで菓子職人の見習いとして仕事を始めていますね。きっかけはなんだったのですか? またパリでは、職人を目指す若者のために早くから学べる環境が整っているのですか?
フランスでは職人見習いには、通常16歳から就くことができます。僕の場合はちょっと特別で、僕は学校では落ちこぼれだったものですから学校の教育担当の人が、「君は早くから職人になるための研修や見習いを始めた方がいい」と、勧めてくれました。それこそが、僕の人生を救ってくれたと今は思います。映画でもわかるように、母親との家族関係というのはうまくいっていませんでしたから、やはり何か目標を持って厳しい環境の中で、どうにか前に進んでいくということが僕自身には必要だったのだと思うんです。そういうふうに若いうちから見習いになれる環境が整っているということを言えば、フランスに育ったことは本当に良かったなって思います。特に、お菓子業界の研修はとても厳しい世界ですから。

映画の中で、若くして研修を積むヤジッドさんに対して、偉大なパティシエたちが厳しさと愛情をもって、そのがんばりを支えてくれましたね。子どもたちが「がんばること」と向き合うために、大人はどのように子どもを見守っていくべきだと思いますか。
子どもというのは、まだ未熟な存在なんです。その未熟であるということは、僕はとても大事でとても素晴らしいことだと思っているんです。子どもが未熟であるということは、欠点ではなく美点です。子どもたちには、これからどういうふうな道を選ぶか、まだまだ未知なもの無知なものがあるわけですよね。そういう中で、大人が良い道をちゃんと示してくれれば、子どもというのはどんどんと吸収していくと思うんです。その中で大切に伝えるべきことは、人生における価値についてだと思います。情熱を持って何かに向き合うことだったり、真面目に勉強したり仕事をしたりすること、そして謙虚に生きていくこと。そういうふうな価値観というものを、子どもたちに伝えることこそが大切なんじゃないかと思うんです。
もう一つ言いたいことは、僕自身が2004年にパティスリー世界選手権で優勝した時もそうでしたが、現代というのはSNSとかテレビとか、すぐに有名になることができるツールがあって、有名になればスターとしてもてはやされます。でもそれってとても危険なことなんです。あっという間にスターになったら、落ちていくのもとっても早いですから。だから、“有名になること”を目標にしてはいけないんです。大切なのは努力、他人をリスペクトすること、そして学ぶことです。学ぶチャンスがあるのなら、文化的な教養というものを子ども時代にきちんと身につけて、それをどんどん吸収してほしいなと思います。

映画では、少年だったヤジッドさんが成長していく過程で「誰かから認められること」が、次第に大きな力になっていくことを感じました。子どもにとって、自分の理解者がそばにいることも、やはり大切なことでしょうか。
もちろん、理解してくれる人たちに囲まれていることはとても大事です。でもそれ以上に、やっぱり自分自身で自分を磨き上げよう、自分の人生を自分で築き上げようという、本人の情熱や姿勢みたいなものの方が大事です。僕自身がそうでした。もちろん里親もいましたし、困難を抱えている子どもたちが集まる養護施設にも入っていたわけですけれど、でもそういうところでは、自分を理解してくれるなんてことは期待ができないんです。だからこそ、そのような中で僕は僕自身のことをたくさん学びました。
メタファーとしてとても好きなのは、赤ちゃんを深いプールに入れた時、赤ちゃんは本能で自然に泳ぐということ。僕自身も何もわからないまま世界に放り出されたので、とにかく泳ぐしかなかったと思っています。本能を頼りに、自分で自分自身を作りあげていくしかないと、強く思いました。そういうふうなやり方で、自分を築きあげることができたと思っています。

現代では、失敗を恐れて自己表現ができないでいる子どもも多いようです。「思い切り頑張ること」や「自分を表現すること」の大切さを、ヤジッドさんはどう考えますか。
怖がるがあまり試すことなくして失敗をするならば、怖い中でも実行をして失敗をした方が、よっぽど得るものが大きいと思っています。僕自身は日々、とにかく怖がらない、どんどん前に進むことを意識しています。「今日は昨日よりいい、明日はきっと今日よりいい」、そう思って毎日を過ごしています。大切なのは「やりたい」という気持ちと、扉を開ける勇気です。
エピソードを1つ話すと、2017年にルイ・ヴィトンとコラボレーションをしたんですが、それは世界選手権で優勝してから、わずか3年後のことでした。僕はアヴィニヨンにお店を持っていて、パリには一度も進出したことはなかったんですが、ルイ・ヴィトンのことはよく知っていましたし憧れがありました。インターネットでLVMHの代表がベルナール・アルノー氏だと知って、彼に一度、僕のデザート食べてもらいたくてオフィスに行ったんです。でも会うことはかなわず、ちょうどクリスマスのシーズンだったので、その時に渡したかった薪の形をしたブッシュドノエルをそのままSNSにアップをしました。そうしたら、それを見てくれた人がどういうわけかアルノーさんとつないでくれて、クリスマスの夜にアルノーさんが僕を招待してくれたんですよ。もちろん、渡したかったブッシュドノエルをもう一度作って持っていきました。
そういうふうに、自分がやりたいんだ、これをしたいんだと、そう思えることがあるのなら、どんな形でもいいから自分で扉を開けることが必要だと思うんです。扉を開ける勇気を持つこと、それは僕自身が今日までずっとやってきていることです。

ヤジッドさんはSNSで、「もう一度人生があったとしても、まったく同じ子ども時代を選びたい」と書いていましたね。その思いの理由を、教えていただけますか。
そうなんです。もちろん、辛いことの多い幼少時代でした。母の問題や、養護施設に入っていたという点では、とても思い出したくもない事柄もたくさんあります。でも僕には、チャンスが目の前に現れた時、それを思い切りやってのけるという大胆さがあったんですね。それはきっと、家族がいないからこそだと思うんです。僕には家族がいなかったから、自分にとっての限界がなかった。これはしてはいけないという制限もなくて、14歳、15歳でも、どこに行ったって構わないというような人生でしたから。
おかげで、責任感というものは与えられるものではなく、自分で持つものだということを、本当に早い時期に体験ができたと思います。今となって思えば、あんなに苦しいことがあったとしても、ああいうカオスのような混沌とした幼少時代を過ごしたとしても、それらがプラスに働いたということがわかります。辛い経験をしたからこそ素晴らしい人生を送れる、という方がいいじゃないですか。だから、僕はいまとても幸せだと思えるんです。

映画の中で登場する“パリ・ブレスト”も“フォレ・ノワール”も、典型的なフランスのデザートと見た目がまったく異なるものでインパクトがありました。パティシエたちは伝統的なお菓子も自分流に作り変えるものなのですね。伝統を受け継ぐことと、そこに新しさを加えること、そのバランスについてはどのように考えていますか。
お菓子作りでは、伝統的なものに対して新しくするというより、自分の個性を添えること、自分のパーソナリティを加えていくことがとても大切だと考えています。上手な菓子職人と、素晴らしい菓子職人との違いというのはその点にあると思っています。伝統的なものを自分のものとして習得して、それをそのまま受け継ぐこと。それはとても才能のあることですけれど、そこに自分の魂を込める、自分の愛を込める、自分の個性を込めていくことによって、そのような伝統のコード、規則、ルールというものを乗り越えて、また新しい、その人にとっての完璧なバランスを見つけることが大切なんです。
そのようなことを、召し上がっていただいた時にも感じていただけるようにと僕自身はいつも考えて作っています。だからおっしゃるように、パリ・ブレストやフォレ・ノワールといった伝統的なお菓子も、軽やかさがあって舌触りや食感がいいだけではなく、たとえばちょっとファッショナブルなデザインを加えるなど、僕自身の個性というものをお菓子を通して伝えることができるんですよ。
幼少時代に作っていたのは、とにかくシンプルな材料で素朴な味でした。貧しかったというのもありますけれど、ものすごく謙虚に作っていたというのがあります。だから今となっては、そこにちょっとファッション性を加えることは、僕自身の子ども時代のオマージュでもあると同時に、乗り越えた自分に対してのオマージュだと思っているんです。

デザートは、人の気持ちを豊かにしてくれるものですが、あなたにとって「豊かさ」とはどのようなことですか?
里親のおじさんが、「デザートいうものはなくてもいいものなんだよ」と、ある時言ったんです。「お利口にしていたらあげるけど、お肉とかお魚とかきちんと食べていたらそれで食事は十分なんだ」と。でもその話の裏には、お菓子やデザートを食べることが、いかに特別なことかを言いたかったんだと思うんです。誕生日、結婚式、クリスマス、人生にとって最高のタイミングでデザートやお菓子というものが供される。それを作れるなんて、なんて素晴らしい職業だろうと子ども時代に思いました。
コロナ禍の時、街がロックダウンしていて買い物もできないし、レストランで食事もできなくて、皆の気持ちが落ち込んでいた時がありましたね。でもあの時フランスでは、お菓子の購買率が30%も40%も伸びたんです。食べることの喜びを満たしたいという人たちがきっと多かったんですね。デザートには、そういうふうに、人の心をおいしいもので満たすことによって、人を癒す豊かさがあるなと思います。

世界中からオファーが絶えない今は、デザートやお菓子に対してどのようなことを考えていますか。
お菓子は、文化を伝えるひとつの媒体だと感じています。例えばフランスであったら生クリームやバニラ、それだけじゃなくて地方の特徴があります。今はさまざまな国に呼ばれて行くことができるようになって、文化と結びついたお菓子について、さらに強く感じています。それぞれの土地で生まれた食材が、お菓子という文化になっているのには本当に興味深いものがあります。日本には、素晴らしい小豆がありますよね。そういうふうに、世界各地の知らなかった食文化を、お菓子を通して発見していくのも、デザートが持つ豊かさなのことだ実感しています。

Yazid Ichemrahen(ヤジッド・イシュムラエン)
1991年フランス、エペルネ生まれ。モロッコ生まれの両親を持つが父親は不在で、母親はアルコール依存症だったため2歳半からホストファミリーに預けられる。ホストファミリーの息子がパティシエだったことで、お菓子作りを経験する。8歳で里親の元を離れ、養護施設で暮らす。14歳の時パティシエとしての見習いを始め、17歳でパリにある「パスカル・カフェ」へ。1年後には、モナコにあるジョエル・ロブションの「ル・メトロポール」のスーシェフとして働く。世界的に有名なシェフ、アラン・デュカスのもとで働いた経験を持つ。2014年、22歳でフランスチームとして参加したGalato World Cup(冷菓世界選手権)で世界チャンピオンとなる。現在、アヴィニヨンに自身の店舗を構えるほか、ギリシャ、スイス、カタールなどに店舗をオープンし実業家としても活躍する。ディオール、ルイ・ヴィトン、バルマン、ショーメなどのハイブランドとのコラボレーションも話題になった。著書に『Un rêve d’enfant étoilé: Comment la pâtisserie lui a sauvé la vie et l’a éduqué(星の少年の夢:菓子作りが彼を救った理由)』、『Créer pour survivre et vivre pour ne pas sombrer(生き延びるために創作し、沈まないために生きる)』がある。

『パリ・ブレスト 〜夢をかなえたスイーツ』
監督:セバスチャン・テュラール 脚本:セドリック・イド
出演:リアド・ベライシュ、ルブナ・アビダル、クリスティーヌ・シティ他
2023年/フランス映画/110 分/配給:ハーク、配給協力:FLICKK
後援:在日フランス大使館/アンスティチュ・フラン セ、日本スイーツ協会
2024年3月29日より、ヒューマントラストシネマ有楽町ほかロードショー
Photograph:Koomi Kim
Text: Miki Suka