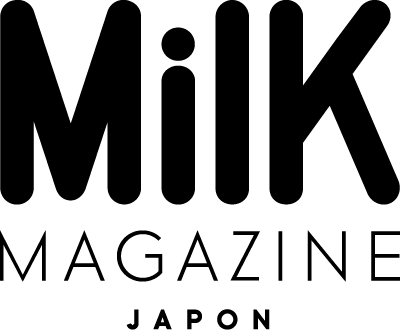初期は違和感を撮り続けていたが、答えは出ないと石内都さんは言う。それでも撮り続けたのは、答えではなく納得するため。その手段である写真へと導いたのは、育った原点であり嫌悪感のあった横須賀。そこを感覚のまま撮り、暗室で吐き出すようにプリントした1枚が、この少女の写真だ。
「撮るのは一瞬。私にとって大事なのは、暗室に篭り吐き出す過程」石内都
少女の写真は、石内都さんのデビュー作である写真集『絶唱、横須賀ストーリー』の中の1枚。横須賀の街を歩いていたら不意に走ってきた少女を、ノーファインダーで撮ったもの。撮れたのはこの1枚だけ。そのまま少女は走り去っていったという。
「このテーマを考えた時に、ふとこの写真を思い出したんです。この少女を見て、『都そのものみたいだね』と何人かに言われたことがあるので。まったく知らない子どもなのにね。私自身も気に入っている写真です」
石内さんが子どもというものを考えた時、思い浮かぶのは自分自身が幼少期を過ごした横須賀の街。その横須賀を“敵討ち”のように撮ったことで、この写真集ができあがった。
「横須賀に住んでいたのは、6歳から19歳くらいまでの13年間。多感な時期を過ごしているので、精神的なものは横須賀から受け継いでいると思う。私はね、横須賀が大嫌いだったの。6歳で移ってきたから、基地が発していた変な匂いみたいなものやおかしなところを、子どもながらに強く感じていました。歩いてはいけない通りがあったり、自分が女であるということを否応なしに基地が教えてくれたんです。たまたま暗室や機材を譲り受けたので、写真を撮ってみようと思った時、やっぱり自分の足元である精神的なものを築いた風景を、もう一度ちゃんと見つめ直さなきゃいけないと思いました。それでカメラを持って横須賀へ。私にとって見つめ直すための個人的な手段が、たまたま写真だったんです」
嫌悪していた横須賀の生活ではあるが、それは原点でもある。そこを客観的に見つめ直すことで先に進みたかった石内さん。
「撮るのは一瞬。シャッターを切るだけだから。私にとっては、暗室にこもって吐き出すという行為が最も大事だったんです。1ヶ月かけて400枚くらい焼き続けました。暗室で30歳の誕生日を迎えたことをよく覚えています。じわじわと写真が浮き上がってきた時の感覚がすごくいいなぁと思ったんです」
普通の美しさではなく、違和感や日陰や淀み、わだかまりに惹かれる
横須賀へ敵討ちに出かけた石内さんは、何に対してシャッターを押したのだろう?
「一瞬ではあるけれど、ひとつの行為だから、何か気になる瞬間に反射的にシャッターを押しているという感じ。ちょっとした違和感みたいなものを写していた気がします。もともと日向と日陰なら、日陰に興味があるんです。人が通り過ぎてしまうような部分、薄暗さ、わだかまっているもの、空気の淀み、そういうものに幼少期の頃から惹かれがち。空気が重たいと感じる道が通学路にあったり、なんか変だな?という場所が身近にたくさんあり、そういう尋常じゃないものに興味があるんです。普通の美しさには惹かれない。それは幼い頃から今までずっと不変の部分。横須賀で育ったことが大きく影響していると思う。その感覚を持ったまま、今まで写真を撮ってきています。写真は、距離がないと撮れない。一体化とはまた違うんです。非常に冷徹なものであり、そこがすごくおもしろいんです」
今、大きな個展を控え、自分の写真を整理しながら、写真についてもう一度考えたいと思っているという石内さん。
「プリントは、私にとって身体的なもの。そこを含め、今までの写真を見直しながら、写真について考えています。写真は、捨てないと残る。逆に写真が残っていないことは、その過去はないのと同じようなもの。写真って証拠なんですよね」
石内さんは笑いながら呟く。
「写真について考え、向き合い、今ようやく写真に目覚めてきたのかもしれない」
photograph ©Ishiuchi Miyako「絶唱、横須賀ストーリー #98」
石内都
1947年群馬県桐生市生まれ。1979年に『APARTMENT』で女性写真家として初めて第4回木村伊兵衛写真賞を受賞。2005年、母親の遺品を撮影した「Mother’s」で第51回ヴェネチア・ビエンナーレ日本館代表作家に選出。2007年より現在まで続けられる被爆者の遺品を撮影した「ひろしま」も国際的に評価され、近年は国内外で作品を発表している。
Interview&Text: Maki Kakimoto