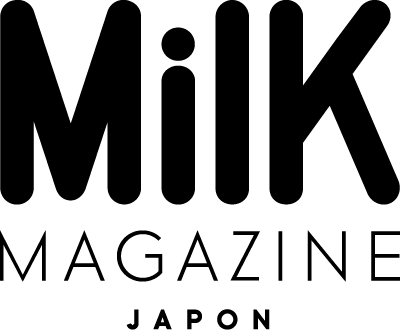家族のカタチが多様になってきた近年、家族で楽しむファミリー映画もファミリーを描く家族映画も、いろいろで面白い。そんな“新しいファミリー映画”を、コラムニストの山崎まどかさんがピックアップしてご紹介します。
『フェイブルマンズ』映画に写しだされる真実の力
コロナ禍でロックダウンを余儀なくされた日々は、様々な映画監督に内省の機会を与えたのでしょう。最近、自分の家族を振り返った自伝的な作品を発表する人が増えました。スティーブン・スピルバーグもその一人です。
舞台は1950年代から60年代にかけて。映画に夢中で、8ミリで作品を撮ることに没頭している少年サミーを中心にして、『フェイブルマンズ』はスピルバーグの家族をモデルにした人々のクロニクルを綴っていきます。
科学者の父バートはコンピューターの天才で、学術肌。優しいけど現実主義者で、サミーの映画熱も一時のことだと見なしているところがあります。一方、コンサート・ピアニストになる夢を諦めた母ミッツィは天真爛漫で、少女のような人。サミーの想像力は彼女譲りなのでしょう。二人を演じるポール・ダノとミシェル・ウィリアムズが衣装を着て現れた時、自分の父母にそっくりなその姿を見てスピルバーグは泣いてしまったと言います。
衣装を着た姿で監督を泣かせてしまった俳優がもう一人。“ベニーおじさん”役のセス・ローゲンです。“おじさん”と言っても彼はフェイブルマン家と血のつながりがあるわけではありません。しかし、父バートの親友のベニーは、サミー少年と三人の妹たちにとっては紛れもない家族。彼はバートの転職で一家がニュージャージーからアリゾナに引っ越す時もついていきます。
そんな家族同然のベニーと母の切ない事実に、サミー少年は家族旅行を撮ったフィルムを編集していて気づきます。彼の作品に映し出されたことが、家族の離散を招いてしまうのです。それは彼が大人の憂いを知る過程でした。
父親についてカリフォルニアに向かうサミー少年と、ベニーの別れのシーンが印象的です。ベニーの茶目っ気と包容力を描くその場面に、彼のモデルとなった人物に対するスピルバーグの愛が伝わってきます。とても複雑な関係だけど、彼はやはりサミーにとってかけがえのない家族の一員なのです。そこに映画に映し出された真実があります。

『フェイブルマンズ』
初めて観て以来、映画に夢中になった少年サミー・フェイブルマン。8ミリカメラを手に、家族の日々を記録したり、妹や友人と映画を製作したりしながら成長する。ピアニストの母ミッツィは彼のクリエイティビティを応援し、エンジニアの父バートは映画作りは趣味に過ぎないものと考えている。正反対の性格の両親の確執はやがて否定できないものとなる。そしてサミーの撮影する映画は、家族の運命を、サミーの未来を変えていく。名匠スティーブン・スピルバーグが自身の子ども時代にインスパイアを受けて製作。
監督:スティーブン・スピルバーグ
出演:ガブリエル・ラベル、ミシェル・ウィリアムズ、ポール・ダノ
© 2022 Storyteller Distribution Co., LLC. All Rights Reserved.
ブルーレイ&DVD発売中(5,280円)
発売元: NBCユニバーサル・エンターテイメント
※Amazon Prime、U-NEXT他でも配信中
公式サイト

山崎まどか
15歳の時に帰国子女としての経験を綴った『ビバ! 私はメキシコの転校生』で文筆家としてデビュー。女子文化全般/アメリカのユース・カルチャーをテーマに様々な分野についてのコラムを執筆。著書に『ランジェリー・イン・シネマ』(blueprint)『映画の感傷』(DU BOOKS)『真似のできない女たち ——21人の最低で最高の人生』(筑摩書房)、翻訳書に『ありがちな女じゃない』(レナ・ダナム著、河出書房新社)『カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ』『ノーマル・ピープル』(共にサリー・ルーニー著/早川書房)等。
text: Madoka Yamasaki
illustration: Naoki Ando