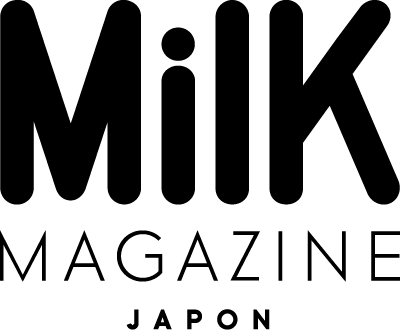「被写体を一所けんめい見る、そして撮る。そうすれば写真はただの『記録』ではなくなる」戎康友
——実家は祖父の代から続く写真館だったという写真家・戎 康友さん。ファッション、広告の世界で撮り続けながらも、自身の中には「ポートレート」というスタイルが軸としてあるという。「見る」という純粋な行為を追求する戎さんのスタイルは、「INNOCENT VIEW」というテーマそのものであるように思えた。——
時間を忘れるほど夢中になったのは、子どもの頃以来だった
語弊があるかもしれないのですが、僕は、自分が写真を撮る理由や、僕の写真を見た人がどう思うか、ということをあまり考えてこなかったんです。そもそも写真家になりたいと思ったことがなかった。子どもの頃から、写真があまりにも日常の身近なところにあったからです。実家が写真館なのですが、始めたのは僕のおじいちゃん。戦時中、満州の食堂で働いていた時にたまたまカメラを持っていて、日本の軍人さんたちの写真を撮って故郷の親御さんに送るということをやっていたそうなんです。そうしたらお礼の品物や手紙をたくさんいただいて「これは仕事になる」と思ったらしく、日本に帰ってきて地元の長崎で写真館を始めたというわけです。
3歳くらいだったと思いますが、暗室の記憶があります。親父に棚の上に乗せられて、そこに座ったまま親父の手元の印画紙にモノクロの像が浮かび上がってくるのを見ていた。その光景を今でも鮮明に覚えています。もう少し大きくなってからは、写真館の仕事を姉と妹と一緒に手伝っていましたね。写真をカットしたりネガを袋に入れたりといった作業を、6畳の部屋のこたつの上でやっていたわけですよ(笑)。
僕自身の子どもの頃からの憧れは、映画の世界でした。撮影の舞台裏をテレビで見たりして、大人がたくさん集まって真剣にやっている様子が楽しそうだと思ったんです。それで大学は映画学科に行きたいと親に伝えたら、写真学科に行けと言われてしまって。でも調べてみると1年くらいで簡単に転科できることがわかった。だったら途中で転科すればいいやと、日藝(日本大学藝術学部)の写真学科に進学しました。入学後早速、映画サークルに入って8mmで作品を撮ったりもしたんですが、大学1年生の夏に雑誌『anan』の撮影アシスタントのアルバイトを始めたら、ファッションの撮影現場の方が楽しくなってしまった。モデル、スタイリスト、ヘアメイクなど、たくさんの人とチームになって、みんなでどこかに辿り着こうとするその仕事が、映画のメイキングの世界に憧れていた自分にしっくりきたんだと思います。朝の5時に撮影現場に入って、終わる頃に時計を見ると夕方の6時、7時になっている。こんなに時間を忘れて何かに夢中になったのなんて子どもの頃以来じゃないか、と気づいて。その時、この仕事が好きかもしれないと思いました。18、19歳くらいの頃です。
撮るということは被写体と「対峙」するということ
僕は撮影する時はいつも、目の前にあるものに対して反応しようと思っているふしがあります。ファインダーを覗いて構図だけ決めると、あとはずっと被写体の顔を見ている。見えないものを写そうとするタイプではないです。人間の目の焦点距離は、レンズ換算でいうと42mm。きっちり42mmというレンズのサイズはないんですが、僕はだいたい42~45mmを使うようにしています。これは、映画監督のヴィム・ヴェンダースが「自分の目で見ているものに一番近いから」という理由でそのレンズを選んでいるというのを読んで影響を受けたからなんです。そういうレンズを使うと、バストアップくらいで人物を撮る際には被写体にかなり近づかないとならないんですが、「この距離感で人と対峙できない限り、写真を撮っているとは言えないんじゃないか」と思っていました。
22歳の頃にニューヨークに行って、初めて自分の作品としてトライベッカの人たちのポートレートを撮りましたが、その時もそう強く思っていました。長い玉(望遠レンズ)を使えば遠くからでも撮れますが、被写体も逃げていくし自分も被写体から逃げているような気がしたんです。
ファッション写真だったら服を見せることが一番大事で、さらに着ている人も格好良く、写真的な魅力を持った人に見えないといけない。頭の中では「表情はこう、手の動きはこうがいい」とレイヤーを重ねるように考えますが、目の前にいるその人自身をよく見てシャッターを切らないと、変に作り込んだような写真になってしまう。今の僕にとって「対峙する」ということは、被写体を美しく捉えるためにどうディレクションするか、ということでもあると思います。
ひとつのものを一所けんめい見る。風景だってポートレート
自分の写真について、以前からずっと「ポートレートを中心に撮っています」と説明してきました。僕はポートレートを「ひとつのものを一所けんめい見る」ものだと解釈していて。例えば、写真館で撮るポートレートは、ある瞬間の、ある家族や人物の姿を記録するものですが、被写体を一所けんめい見て撮ることで写真はただの「記録」ではなくなる。後から振り返った時に「あの時はああだった、こうだった」と懐かしむに足るものになると思うんです。
キャサリン・オピーはポートレートで有名な写真家ですが、家を撮影したシリーズもあって、彼女はそれを「家のポートレート」と言っていました。風景写真だって、撮る人の意識次第でポートレート写真なんです。下の写真は、イギリスの作家、ヴァージニア・ウルフの姉のヴァネッサ・ベルの庭を撮ったものです。この仕事をいただいた時、仕事であまり風景写真は撮っていなかったのですが、いつも通り「ひとつのものを一所けんめい見る」ということを心がけて撮りました。「写真が好きで好きでたまらない」という人はたくさんいます。でも僕は、そういうものすごく熱い気持ちは持たないでやってきました。ただ、これしかできないからやっている。写真館で過ごした子ども時代があって、僕にとって写真は本当に水や空気のように「そこにあるもの」でしたから、写真を仕事にするようになったのは自然の成り行きだったといえます。だから、原点、原風景は、なんて聞かれると、自分にはちょっと大袈裟な気がしてしまいますけどね。

戎康友
1967年長崎県生まれ。日本大学藝術学部写真学科卒業後、写真家として独立。アメリカやヨーロッパを旅しながら現地の人々を撮影したポートレート作品を発端に、ファッション誌のエディトリアルを中心に、広告、アーティスト写真までを幅広く手がける。近年の作品集に『KAMO HEAD』(2021年)、『村上T』(2020年)『、bones』(2014年)がある。今年7月から9月まで、OFS Galleryにて川内倫子、鈴木理策、テリ・ワイフェンバックとのグループ展『photography&us』を開催。過去に撮りためていた、デレク・ジャーマンをはじめイギリスの文化人や貴族の庭を撮影した作品を発表した。
Interview&Text: Chiaki Seito
Photographs ©️Ebisu Yasutomo