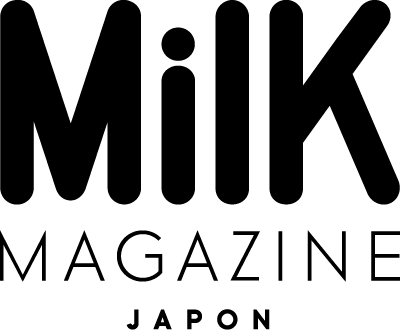家族のカタチが多様になってきた近年、家族で楽しむファミリー映画もファミリーを描く家族映画も、いろいろで面白い。そんな“新しいファミリー映画”を、コラムニストの山崎まどかさんがピックアップしてご紹介します。
ふたつの家族の愛、それぞれの明日『1640日の家族』(7/29全国公開)
夏の行楽地、大型レジャー施設のプールで遊ぶ2組の家族。そのうちのひと組は、3人の男の子を抱えるドリスとアンナの夫婦。しかしよく見ていると、一番下で6歳のシモンだけ少し違う環境にいるのが分かります。アンナは日曜には彼だけを連れて教会に行き、家でも長男のアドリと次男のジュールが相部屋を使っているのに、シモンだけが個室をもらっています。シモンは生後18ヶ月でドリスとアンナに預けられた里子でした。妻を亡くした後、どうしてもひとりで子どもを育てられなかった実の父エディとは、月1回の面接日に会うだけの日々。ようやく悲しみが癒えて家族を養う準備ができたエディは、再びシモンと暮らすことを希望します。
様々な理由で子供と暮らせなくなった親が、他人の家庭に子供を預ける里親制度。養子とは違い、最終的には実の親と子供が暮らせるように手を貸すのがルールです。でも物心ついたときにはもうドリスたちと暮らしていたシモンにとっては、彼らは家族以外の何者でもありません。特にシモンが「ママ」と呼んでいたアンナとの絆は深く、彼女も手塩にかけた我が子のようなシモンを手放す気にはなかなかなれない。
監督のファビアン・ゴルジュアールの両親も、生後18ヶ月の子どもを里親として受け入れ、彼はその子どもと一緒に過ごしてきた経験があります。アンナたちとシモンの関係を深く理解しているはずです。血はつながっていなくても、彼らは暮らしを通して絆を築いてきた間柄。一方、エディは実の父親であるのにもかかわらず、一から家族としての関係性を息子と築いていかなくてはならない。郊外に家を持つアンナたちと、都市部の集合住宅で暮らすエディの経済格差も垣間見えて切なくなります。
どうすればシモンが一番幸せか。同じことを考えているはずなのに彼のふたつの家族、特にアンナとエディはぶつかり、時にシモンを混乱させ、悲しい思いをさせます。きれいごとなしで、子どもを想って傷つく大人の姿を見せたこの映画から、幼い自分を育ててくれた里親と実の両親、監督の両方の家族への愛と感謝が伝わってくるようです。

『1640日の家族』
生後18ヶ月のシモンを受け入れた里親のアンナと夫のドリス。息子のアドリとジュールとは兄弟のように育ち、幸せな4年半が過ぎようとして いた。ところが、実父のエディからシモンを手元で育てたいと申し出が。突然のことに戸惑う家族をよそに、エディの生活再建を見守ってきた児童 社会援助局は、シモンの家庭復帰の手続きを粛々と開始する。“末息子”に惜しみなく愛を注いできたアンナは、週末の宿泊で子育ての大変さをこぼしたエディに不信感をつのらせる。一方シモンは愛情豊かで賑やかな里親家庭と、産みの母について教えてくれる実父の間で揺れる。2つの家族の選択は……。
監督/脚本:ファビアン・ゴルジュアール
出演:メラニー・ティエリー、リエ・サレム、フェリックス・モアティ、ガブリエル・パヴィ
2022年7月29日(金)TOHOシネマズ シャンテほか全国公開
配給:ロングライド
©︎ 2021 Deuxième Ligne Films - Petit Film All rights reserved.
公式サイト

山崎まどか
15歳の時に帰国子女としての経験を綴った『ビバ! 私はメキシコの転校生』で文筆家としてデビュー。女子文化全般/アメリカのユース・カルチャーをテーマに様々な分野についてのコラムを執筆。著書に『ランジェリー・イン・シネマ』(blueprint)『映画の感傷』(DU BOOKS)『真似のできない女たち ——21人の最低で最高の人生』(筑摩書房)、翻訳書に『ありがちな女じゃない』(レナ・ダナム著、河出書房新社)『カンバセーションズ・ウィズ・フレンズ』(サリー・ルーニー、早川書房)等。